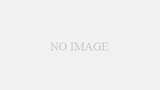宅建で重要な集団規定、次は形態制限、特に容積率についての解説です。
まず形態制限とは、建築物の大きさ、広さ、高さといった主に建築物の外形を規制するものです
その内容として、容積率制限や建ぺい率制限があります。
この章では容積率制限について解説します。
1.容積率制限の意義と趣旨
まず容積率とはどういう意味でしたか?
容積率は、建築物の延べ面積(建築物の各階の床面積の合計)の敷地面積に対する割合をいいます。
この容積率が大きくなればなるほど、階数が多く、容量の大きい建築物の建築が可能となります。
そもそも、容積率制限の趣旨は、建築物の大きさを規制することによって、 建築物と道路、または公共施設等とのバランスを図り、市街地の環境を保護することにあります。
2.容積率制限の内容
ここの部分は具体的な数字が多く出てきますから、注意しながら見ていきましょう。
まず、容積率の数値は、基本的には都市計画によって定められます。
この都市計画は、住みよい街を作るというのがコンセプトですが、そのために用途制限や建築物の大きさについて制限を定めています。
これは、地域、地区の種類によって異なるものとなっています。
なお、○/△というのは、「○分の△」という分数を表しています。
| 地域、地区 | 都市計画で定める容積率 |
| 第一種、第二種低層住居専用地域 | 5/10、 6/10、 8/10 、10/10 、15/10、20/10 |
| 第一種、第二種中高層住居専用地域 | 10/10、15/10、20/10、30/10、40/10、50/10 |
|
第一種住居地域・準住居地域 第二種住居地域・準住居地域・近隣商業地域・準工業地域 |
10/10、15/10、、20/10、30/10、40/10、50/10 |
| 工業地域・工業専用地域 | 10/10、15/10、20/10、30/10、40/10 |
| 商業地域 | 20/10、30/10、40/10、50/10、/60/10、70/10、80/10、90/10、100/10、110/10、120/10、130/10 |
この都市計画で定める容積率の中からいずれかを都市計画で選択します。
しかし、上記の表はあくまでおおまかなものであり、実際に適用するとなると不都合がでてくる場合もあります。
そこで前面道路容積率の登場です。
なんのこっちゃと思われた方、今から解説します。
そもそも、容積率には都市計画容積率と前面道路容積率が存在しています。
では、この2つをどうやって使い分けるのでしょうか?
それは、前面道路の幅員に左右されます。
具体的には、前面道路の幅員が12m以上の時は都市計画容積率、それ未満の時は都市計画容積率と前面道路容積率を比べて、数値の小さい方を用います。
そして、この前面道路容積率は次のような公式があります。
| 前面道路容積率 = 前面道路の幅員 × 法定乗数 |
もしここで、前面道路が2つ以上あった場合は、その幅員の広い方が、この公式の前面道路となります。
次に法定乗数ですが、宅建に合格するには、この意味を知るよりも、実際に数値を覚えて使いこなすことのほうが重要ですので、あまり深い考えは必要ないです。
この法定乗数は地域、地区の種類によって数値が変わります。
以下に表にしてまとめました。
| 地域、地区 | 法定乗数 |
| 第一種、第二種低層住宅専用地域内 | 4/10 |
| その他の住宅系用途地域内の建築物 |
4/10 ※特定行政庁が、都道府県都市計画審議会の議を経て指定する区域内の建築物については6/10) |
|
その他の建築物 |
6/10 ※特定行政庁が、都道府県都市計画審議会の議を経て指定する区域内の建築物については6/10か8/10) |
この数値は絶対に覚えましょう!!
宅建主任者試験では実際に計算する問題も出てくることもあります。そのときに法定乗数がわからないと問題が解けません!
3.建築物の敷地が容積率制限の異なる地域にわたる場合
建築物の敷地が、容積率の異なる2以上の地域などに渡っている場合にどうする?という問題です。
この場合、各地域の容積率を、その敷地の地域内にある各部分の面積の敷地面積に対する割合を乗じて得たものの合計以下でなければなりません。
備考:この章は宅建において重要です。多くの数字が出てきましたが、ちゃんと文章と関連付けて覚えましょう。
あと、その数字は直接覚えるよりも問題を見ながら覚えた方が素直に頭に入ってくると思われます。